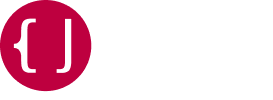【Code for America インターンシップ報告(前編) 】
Code for Japan / Nanto(富山県南砺市)の松本です。
少し前になりますが、Code for Japan(以下、CfJ)も参考にしているCode for American(以下、CfA)に先月2月9日~3月5日の約1か月間インターンシップを行ってきました。
CfAの様子や働いているスタッフ、米国の各Brigadeの活動などについて、松本が感じたことをつらつらとまとめてみました。前編・後編と長めの内容になりますが、ほんの少しでも現地の様子が伝われば幸いです。
松本がCfAでのインターンシップに至った背景
NPO法人ETIC.が12月に募集しておりました「Re-imagineマイプロ海外プログラム」に参加させていただき、プログラムのフェーズ2:海外の企業・団体でのインターンシップ先としてサンフランシスコに拠点のあるCfAを選ばさせていただきました。
今回のインターンシップが実現できたのは、CfA代表の関さんと2年前にWIRED CONFERENCEで日本にもお越しいただいたCfAのスタッフであるCatherine Bracyさんがフランクに連絡が取れる関係があったことが大きかったです。年末の忙しい中色々調整していただき、僕の人生の中でも素晴らしい体験を得ることができました。
シアトルで3週間リーダーシップ・社会起業家の事例を学び、その後の4週間CfAでインターンシップを行いました。*元々CfJとCfAの間でインターンシップを行うと計画していたわけではなく、他の機会を活用してタイミング良く受け入れていただいたカタチです。
2月9日:インターンシップ初日
約2年前にCfAの設立者であるJennifer PahlkaさんのTED Talks 「コーディングでより良い政府を作る」を拝見して以来、Civic Techの活動に関わりたいと考えていました。インターンシップとはいえCivic Techの最前線で活躍されているCfAスタッフの方々と一緒に働けることに胸を高まらせながらサンフランシスコ市内にあるオフィスに足を踏み入れました。

最初のオリエンテーションの中で、私はCatherineさんがリーダーを務めるCommunities teamの配属となりました。Communities teamは、米国内および日本などCode for Allを含むグローバルなBrigadeの支援を行うセクションです。
Communities teamメンバーの紹介ビデオ
インターンシップでの私の役割は、2月21日開催のInternational Open Data Dayと平行して開催されるCodeAcrossの開催までのサポートと、CodeAcross時の各Brigadeの活動内容のキュレーションと分析という役割が与えられました。CodeAcrossでは、各Brigade同士のつながりを深めることを目的としたChallenge(イベント)を提供しています。
僕としてはCodeAcrossの他にも日本に比べ米国で先行している事業であるFellowshipやCivic Tech Startupの支援などについても学びたかったため、業務の合間に各セクションの担当者にインタビューさせていただくことになりました。

オリエンテーション後には、スタッフのみなさんにランチミーティングに誘っていただきました。ランチをしながら「人生での初めての仕事」をみんなで語りました。昨年のCode for Japan Summit 2014のゲストスピーカーで来日していただいたAndrewさんからは「一緒に仕事をしているけど、みんな忙しいのでこういった機会に相手のことを理解するんだ」とおっしゃっていました。元々プログラマだった人もいれば、皿洗い、窓ふき、パンを焼いていた、そして公務員として公園の担当だった方など様々でした。
2月10日:アジアの学生にCode for Japanについてプレゼンテーション
イノベーティブな教育プログラムを提供しているの米国NPO法人VIA(Volunteer in Asia) のProgramに参加しているアジアの学生さんがCfAを訪問。Code for JapanのBrigade支援員のOhno Satomiさんが昨年関わっていたこともあり、日本人大学生を含むアジアの学生さんにCfJの活動についてショートプレゼンをさせていただきました。

英語は不得意な松本ですが、プレゼン後には何人かの学生さんからCfJについて熱心に質問をいただきました。一部の学生さんは、後日Code for San FranciscoのMeetup(Civic Hack Night)に参加していただいたり、3月12日に開催した第63回CfJ井戸端会議にも参加していただきました。まさかサンフランシスコで日本の学生さんとつながるとは思いもしていませんでしたが、10・20代の若者にCivic Techについて興味を持っていただけるきっかけになれて良かったなと感じました。
2月10日:OpenOaklandのCivic Hack Night(1夜目)
インターン中の僕のメンターであるBrielleさんから、彼女の地元であるオークランド市のCivic Hack Night(以下、CHN)に誘っていただきました。
少しCHNについて説明します。
CHNは週一回程度Code for America Brigadeが各自開催しているMeetupイベント。基本的には誰でも参加可能な無料イベントであり、エンジニア・デザイナー・行政職員・そして市民の方が集まり、地域課題やBrigadeの運営について議論やプログラミングなどを行っています。
OpenOaklandのCHNには平日にも関われず約50人がオークランド市役所に集まっていました。日本のBrigadeでも平日夜に運営ミーティングやイベントなどが開催されていますが、数名~10名程度場合が多いだけにその熱気に驚きました。著名な方の講演がある際には、300人が参加した日もあったとか。
オークランド市民のCivic Techへの関心の高さを感じました。

すでに複数のプロジェクトが進んでいることもあり、非常に活発的な議論がされていました。CHNを運営されているコアメンバーの方にインタビューを行った中で興味深いかったことは、コアメンバーの役割のひとつに「ボランティアディレクター」という役職があるということ。初めての参加者へのレクチャーやモチベーションを保つためのアクションをされているそうです。日本のBrigadeではあまり聞いたことはありませんでしたが、重要な役割ですね。
ボランティアリーダーのAshelyさんには当日お会いできませんでしたが、一度参加された参加者はボランティアデータベースに登録するなど、参加者管理までしっかりとされているそうです。日本のBrigadeは運営メンバー = 開発メンバーであることが多いですが、米国のBirgadeは地域課題の議論やアプリの開発はCHNの参加者であり各課題ごとのプロジェクトに参加しています。運営メンバーの役割はイベントの機会や場づくり、参加者のプロジェクトを進みやすいようにサポートすることです。またOpenOakladでは、定期的にコアメンバーの変更や配置変換も意図的に行うことで、様々なことを属人化せずドキュメント化したりコミュニティ文化を定着させるように取り組まれているとのことです。このあたりがCivic Hackerを増やし、持続的な開発を可能にするひとつの環境・文化ではないかと感じました。
またOpenOaklandが開発した有名なwebサイトOpen Disclosureについてもご紹介いただきました。これは、政治資金の可視化サイトです。このサイトを作られた理由としてはやはり市民が政治資金の透明性”transparency”について可視化したいことがきっかけだそうです。
政治資金のデータについては、オークランド市職員でオープンデータ化され、OpenOaklandはアプリ側の開発・メンテナンスを行っているとのことでした。
2月11日:Show’n Tell
毎週水曜日のCommural lunch(CfAがスタッフに提供する無料ランチ)後に開催されているShow’n Tellに参加。
CfAのスタッフはそれぞれのセクションで働いているのですが、Show’n Tellはチームの枠を超えたの発表会です。

「○○市の△△の位置情報がオープンデータ化されたからOSMにプロットしてみた」というwebサイトの紹介や「カッコいいスライドのテンプレート作ってみた」などの紹介がされていました。
基本的には成果発表というよりも「とりあえずやってみた!」「こんな感じで進めているけどフィードバックが欲しい」的なプレゼンが多かったです。僕が素晴らしいなと感じたのは、紹介された中には「え、これだけのことなの?」といったものもまずは作ったことに対して賞賛するということでした。すぐに「良い・悪い」のJudgementをするのではなく、まずそのプロセスを認めるということが、持続して新しいのを創り始める・続けるに必要ではないかと感じました。
この点は彼らから見習う姿勢のように感じました。
2月11日:Code for San FranciscoのCivic Hack Night(1夜目)
今回滞在したSan FranciscoにももちろんBrigadeがあります。エリアがSFなだけにCfAのオフィスで毎週CHNが行われています。
松本としては徒歩0分で会場に到着できましたのでとても楽でした(笑)
昨日のOpenOaklandに比べるとよりカジュアルな雰囲気で行われており、日中は封印されているCfAオフィスのビアサーバも解禁されビールやケータリングを楽しみながらCHNが進んでいました。

当日は来週のCodeAcrossに向けたプロジェクトのお知らせ、既存のプロジェクトの開発、初めてのCfSF参加者向けのイントロダクションに分かれてMeetupが行われました。
Code for San Franciscoは今年の大きな地域課題テーマは「Housing」
サンフランシスコ市内の住宅に関する課題をテーマにプロジェクトを進めているとのことでした。
2月17日:OpenOaklandのCivic Hack Night(2夜目)
先週に続き、OpenOaklandのCHNに参加。
今週も各プロジェクトがもくもくと進んでおりましたが、その中でProject DirectorのRonaldさんのプロジェクトふりかりのワークショップが興味深かったです。
「みんな少しの時間、前にあるグラフにプロジェクトに対する想い・考えをシールで貼ってほしい」と全体共有の際にRonaldさんが発言。

何かと思い見に行くと、OpenOaklandの各プロジェクトを縦軸にとり、「VISION」「EXECUTION」「IMPACT」の領域で、メンバーの気持ち(”もっとやるべきだ”は黄色もしくは赤色、”もうだいぶできている”というものは緑色か青色)を貼って現状のメンバーのテンションや方向性を可視化するというエクササイズでした。その後、Ronaldさんで、シールの貼っている内容をクラスタ分析・パターン認証することで今後のプロジェクト運営にフィードバックされるとのことです。
アナログながらも、シンプルで簡単そして2回目参加の松本でもプロジェクトがどのような方向に進んでいるかわかりやすいリフレクションだと感じました。たとえば、「IMPACT」のグラフだとOpenDisclosureはもっとGlobal(広く世の中に)使われるようにしたい、Summer JobsはもっとLocal(オークランド市内のコト)にフォーカスしたい、といった感じです。
日本の各Brigadeではまだプロジェクト自体の数が少ないかもしれませんが、IODDやCodeAcrossが終わった際にメンバー間でのふりかえりで試してみてもいいかもしれません。
2月18日:Code for San FranciscoのCivic Hack Night(2夜目)
先週のCfSFのCHNでキャプテンのJesseさんよりご依頼をいただき、今週のゲストスピーカーとしてSF市民の参加者にCfJの活動について約5分ほどのプレゼンをさせていただきました。

ざっと見渡した限り六本木にありますGLOCOM国際大学の会場と同じくらいのような気がしたので40〜50名ほどの聴衆だった気がします。
日本のBrigadeの事例や、現在行っている福島県浪江町のフェローシップの概要についてざっくりとですがお話させていただきました。プレゼン後のQAタイムでは以下のような質問をいただきました。
・Code for Namieのソリューションはオープンソース化の予定はあるのか?他の地域でも使えないのか?どんなサポートをCfJは今後予定しているのか?・サンフランシスコも災害のリスクが高いので、Code for Namieの取組みについてもっとディスカッションしたい・日本のオープンデータの推進状況はどうなっているのか?
サンフランシスコ市民の方々は日本のBrigadeの広がりと週末のIODDの参加都市の多さに驚かれていました。
僕もCode for NantoというBrigadeを運営している一人ですが、日本のBrigadeの取組みはまだまだ十分ではない部分もありますが、自信を持って良いのだと改めて感じました。

週末のCodeAcrossでもCfSFの会場スタッフとしてサポートすることになり、初めてのCodeAcrosssがますます楽しみになりました。
2月21日:CodeAcross@San Francisco

改めてCodeAcrossについて説明を。
CodeAcrossはCfAと各CfA Brigadeが主催する2/20~2/22までの期間に開催する各Brigade間の関係を強めるためのイベント。内容(というよりノリ)はIODDに近く、同日に各Brigadeが各自イベントを行うことでお互いの取り組みを知る・関係づくりが目的です。詳細についてはCommunities teamの仕事として日本向け資料を作成しましたので、こちらをご参照ください。また、日本でのIODD・CodeAcross開催のお祝いビデオも作成しました。CodeAcross担当で私のメンターであるBrielleさんよりボストンからいただいたメッセージを編集しました。日本でもいくつかのIODD会場で流していただいたみたいです。
さて、今回は会場スタッフとして参加したSFの様子についてお伝えします。SFは21日のみの一日イベントでした。
気合を入れて1時間前に会場となるCfAのオフィスに到着、スタートの午前9時半に向けて準備を行いました。
当日会場スタッフとして松本が行ったことはこちら。
1.会場案内の貼り紙を作る2.本日行うプロジェクトを模造紙に書き出す3.会場案内のマップを作る4.BGMを選曲・流す(Spotifyのアカウント作成&日本からスピーカーを持ってきてよかった)5.アーカイブとしてビデオや写真を撮る6.イベントハッシュタグである #codeacorss をSNSでつぶやく7.途中から参加された方にイベントのイントロ、進行しているプロジェクトに入るためのサポート8.(オートロックなので)ドアキーパーをする9.他の会場からのCodeAcrossへのメール問合せ対応 など
2.のプロジェクト一覧は最後の全体共有のプレゼンで活用されたり、打上げのBarでも「マップの案内はよかった」など、少しはお役に立てたみたいでよかったです。
さて、CodeAcross@SFはどのような内容だったかというと、特にCodeAcross向けのハッカソンや特別なイベントをするわけではなく、毎週水曜日に開催されているCHNの一日版という形で、新しいメンバーを迎え入れたり、より深いディスカッション・開発をしているといった印象でした。

また、イベントスポンサーのMicrosoftとStarbucksからは朝食と昼食としてコーヒーとケータリングの食事が提供されていました。

今回のCfAがBrigadeに提供しているChallengeプロジェクト「CITY OPEN DATA CENSUS」を含めた13個のプロジェクトが並行で進められ夕方4時からは全体共有がスタート。各チーム報告する内容は以下の2点。「今日何ができたか?」そして「(プロジェクトを進める上で)Brigadeに対して何が必要か?」特に後者は持続的なプロジェクト運営・課題解決には重要なシェアに感じました。
「こんなメンバーに入って欲しい」だけでなく、「もっとディスカッションがしたい」などのシェアも多かったです。そこから毎週水曜日のCHNにつなげて、プロジェクト化に持っていく流れになるのかなと。
CfSFキャプテンであるJesseさんなどがプロジェクトマネジメント/ディレクションもされるのですが、課題を持った方々が当日以降も参加して継続することが大事だなと感じました。
日本では「ハッカソン疲れ」や「プロトタイプ開発後の開発・活動が続かない」ケースが多く聞かれますが、当日以降のCHNなど継続してプロジェクトを行う場を用意することなどは、僕も見習わないといけないなと感じました。
最後に全員ではありせんでしたが、参加者で集合写真を撮影。なぜか松本のトルミーに注目に集まり、トルミーでパシャリ(笑)

他のBrigadeの様子についてはCodeAcross Blog のブログからご覧になります。
私も一部まとめを行いました。