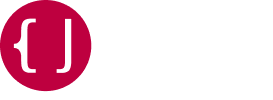【Code for America インターンシップ報告(後編)】
Code for Japan / Nanto(富山県南砺市)の松本です。
引き続きCode for Americaでのインターンシップ滞在についての後編をご報告いたします。
2月23日:Fellewship、Accelerator担当者へのインタビュー
インターンシップの山場であったCodeAcrossもひと段落した翌週、FellowShip担当であるGovernment TeamのBeccaさんとGarrettさんにインタビューさせていただきました。

インタビューさせていただいたGovernment TeamのGarrett Jacobsさん
Fellowshipの事業内容策定やフェローがパフォーマンスを発揮できるようにコーディネートされているお二人。Fellowshipの年間スケジュールは、1月にSFのCfAのオフィスで(主に行政やコミュニケーションに関する)トレーニング、2月に各受入自治体でのリサーチのためSFを離れ、3月の第一週目にSFに戻り残りの任期で開発を行います。まさにこの週は今年の24名のフェローがSFに戻る直前でした。
CfAは5年間で約30都市、100人以上のフェローを自治体に送っており、その取組みについて色々お伺いさせていただきました。
その中で特に興味深かったことは「Fellowshipでの受入自治体を決める際にCfAが一番重要視しているポイントは何ですか?」という松本の質問に対する回答でした。
「受入する自治体にリーダーシップがあるかどうか」とGarrettさん。
この回答からは、CfAは自治体を”パートナー”として捉えている・お互いの関係性を重要視していること、フェローが成果を出すためには自治体側での協力体制や覚悟も求めていることが感じとれました。まだまだCfJの普及活動の中でも自治体からは「何かいいことしてくれるのですか?」といった反応をいただくことがありますが、CfJが目指す「ともに考え、ともにつくる」という姿勢は自治体側でも共有しなければ、Fellowshipは成功しないことを改めて実感しました。
続いて、日本ではまだ事業としては始まっていないGov techのビジネス領域に関するスタートアップの支援をされているContent TeamのDharmishtaさんにインタビューを行いました。

インタビューさせていただいContent TeamのDharmishta Roodさん
Gov techのビジネスおよびビジネス支援を行っている企業に対してCfAがサポートをAcceleratorプログラムですが、事業の概要は以下です。*オープンデータに関するビジネスのみというわけではありません。
・約200時間のトレーニングとメンターサポート(開発・UI/UX、マーケティング、資金調達など)7月-10月の4ヶ月間で実施。
・ビジネスに関するアドバイス
・ネットワーキングとPR(Code for America Summit時でのプレゼンテーションを行う機会の提供)*CfAが営業を支援する、サービスにお墨付きを与えるということではない。
・1チームあたり年間25,000US$(約300万円)のビジネス支援資金 *1US$=120円の場合 など
ちなみにGov techとは、行政の内部プロセス及び作業効率を改善するビジネスや、地域コミュニティに対する行政のサービスを改善および代替するビジネスのことを指しています。CfAの目的である「コーディングでより良い行政を作る」ことに賛同するスタートアップ企業を支援するという事業です。 Gov techの主なビジネスモデルも上記の2パターンであり、主な顧客は自治体になるとのことです。
「Acceleratorプログラムを始めるまでに何が一番大変でしたか?」という質問をDharmishtaさんにさせていただいたところ、「事業を運営ためのスポンサー集め」というご回答でした。現在は、Googleがスポンサーとなっておりますが、Acceleratorが事業として開始したのは、CfA設立から4年目の2012年。Fellowship同様に米国内でもなかなか事業を構築するまでには苦労されたそうでした。ただ、Gov tech、Civic tech共に市場は拡大しているため、より一層Acceleratorの事業は拡大していくであろうとおっしゃっていました。
英語記事になりますが、Civic Techに関するマーケットのレポートです。ご参考まで
2月27日:Code for Americaへの取材対応
きっかけはEvernote日本法人会長を務めてらっしゃる外村 仁さんでした。
日本の友人より外村会長をご紹介いただき、取材前日にEvernote本社をご訪問。
その際にtypeの編集部のお二人にお会いさせていただき翌日にCfAを取材していただくことになりました。

取材当日、CfAのオフィスツアーをコーディネートさせていただき、その後私の理解の許す範囲でCfAについてお伝えさせていただきました。
エンジニアのキャリアについて様々な記事を書かれているtypeですが、ある意味Fellowship自体がエンジニアとしての新しい一つのキャリアである気がしました。JenniferさんのTED talksの序盤にフェローシップのアイデアについて「超人気のエンジニアやデザイナーに1年間休職してもらって彼らが気に入らない職場で働いてもらうというものです」と紹介していたことを思い出しました。
エンジニアに限らず、米国と日本の働き方の違いの大きな特徴のひとつは「行政・ビジネス・NPOなどの領域を超えたキャリア形成」だと感じました。お互いのボーダーを超えることは共創していく上では価値のある経験なのではないかと思います。
取材後、編集部の方より”なぜCivic Techがアメリカで広がっているのか腑に落ちました”とおっしゃっていただいき、ひとまず取材対応した者としてホッといたしました。
どんな記事になるのか楽しみです。
2月27日:コワーキングスペースでともに働いた企業のFarewell Party
「CfAのスタッフの誰か辞めるんですか?」
CfAオフィス内でのイベントや施設管理をされているOperation TeamのCarolinaさんより「Farewell Party(送別会)を夕方に行います」という案内メールを受け取り、近くのスタッフに思わず聞いてしまった松本。
実はこの日まで知らなかったのですが、CfAはオフィスの一部をコワーキングスペースとして貸し出す事業も行っており、今回は2月一杯までオフィスに入っていた地図系オープンソースのスタートアップ企業が別の大きめのオフィスに移ることをお祝いしたPartyでした。Acceleratorプログラムの一環としてGov techのスタートアップ企業にコワーキングスペースの提供をしていることは知っておりましたが、Gov tech・Civic techではない一般企業に対しても貸出を行っているそうです。

まぁ、CfAのオフィスはSF市のダウンタウンの中心からほど近く、確かにビジネスを行う上でも魅力的なエリアですから(笑)余談ですが、CfAのオフィスから最近移転してきたTwitter本社までの距離はわずか2ブロック、UberやAirbnbなどのメガベンチャーも近くにありました。
今回オフィスを移られる企業(すみません、会社名を失念..)の方にCfAのオフィスについて感想をお伺いさせていただいたところ「他の団体と一緒のオフィスで仕事をするのはある意味新鮮で良かった」とおっしゃていました。このような思いもよらない出会いの空間や機会が、新しい可能性を生むのだと感じました。
3月3日:They’re back!
CfAでのインターンシップも残り1週間。
3月に入り、2015年の24名のフェローが1ヶ月間の各地域でのリサーチを終えて全米からSFに戻ってきました。
帰還初日は、全8チームのリサーチについてフェロー・スタッフを交えての3時間の全体共有が行れました。どのようなリサーチが行われていたのか僕も楽しみに参加しました。

各チームのプレゼンを拝聴していたところ、自治体の課題の話ももちろんありますが、どちらかというと実際に行った都市や受入先の地域がどんなところだったのか、どんな人に会ったのか、そしてフェロー自身がどのような生活をしていたのかという体験記に近い内容が多いかったです。 あと途中から気づいたことは1チームを除いて男女混合チームであること。FellowshipのCoordinatorであるBeccaさんに「男女比は意識してチーム構成をしているの?」と質問させていただいたところ、「たまたまバランスが良くなっただけで、特に意識してなかったよ」とのご回答。裏を返せばそれだけフェローに参加する女性も多いということですね。その女性フェローのひとりであり、今年日系人としての初のフェローであるMari Murakiさんにお会いしました。ナント毎年、東京と仙台に来られているとか。

元々大学では数学や統計学を専攻されており、データサイエンティストとして今年ボストン近郊の小都市Somervilleのフェローとして参加されています。教育やコミュニティの情報活用について取り組まれるとのこと。 フェローとしての期間中には、今後5回ほどSomervileに行かれる予定だそうです。
CfJについては、Brigadeの積極的なボランティア活動にインスパイアされたそうです。私にはそこまできっとできないだろうと。
日本人として、Mariさんのご活躍に注目していきたいと思います。
3月4日:イトナブ@Civic Hack Night

2月下旬にCfJ代表の関さんより「松本さん、ちょうどインターン最終週にイトナブがシリコンバレーに滞在しているみたいですのでCfAとイトナブのコーディネートしていただけませんか?」と連絡をいただきました。VIA Program、typeさんに続く3回目のコーディネートとなると慣れたもの(笑)CfAのオフィスツアーとCfSFのメンバーとゲストプレゼンの調整をさせていただきました。当日は私もイトナブのシリコンバレーツアーに1日同行&サンフランシスコの観光案内を行い、夜から開催されるCHNにご案内しました。
プレゼンターの古山さんは英語は苦手とおっしゃいながらも、日本でも愛されているキャラクターでSF市民の笑いを取るあたりはさすが。そして、プレゼン後にはもっとイトナブの話を聞きたいと古山さんに話しかける市民の方もいらっしゃいました。約100年前にもSFでは大地震があり、そこから復興をした歴史を持つ市民とっては、イトナブの活動や石巻に与えるインパクトについては関心があり、質問されたようでした。

古山さんと一緒シリコンバレーを回っている若手メンバーも英語は苦手だと言いつつも、どんどんグループの方々に話かけていく若者の姿はたくましく見えました。また、英語ができるメンバーは普通にプロジェクトミーティングの飛び込んでみたところ、最後にはプロジェクトメンバーにならないかと誘われていました(笑)

”至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり”
そう感じさせられるイトナブのCHN参加の夜でした。
ちょうどCHN参加した日に朝日新聞に紹介されたイトナブの記事はこちらから
3月5日:インターンシップ最終日 CfAスタッフを前にプレゼンテーション
CfAのインターンシップ最終日。最終日であった木曜日午後1時~2時の時間帯はスタッフ全員参加の定例スタッフミーティングなのですが、その最後にCfJについて約15分間プレゼンさせていただきました。
プレゼン前には、Communities Teamでお世話になったHannahさんから、CfAのジャージとロゴ入りの万年筆をいただきました。

英語でのプレゼンテーションはインターン中に5回ほど経験したこともあり、ある程度プレゼンの中でアドリブを織り交ぜることもできるようになりました。スタッフだけでなく、Mariさんをはじめとする2015年のフェローの方も出席いただいため、改めてCfJのこれまでのBrigadeと浪江町でのフェローシップの取り組み、そして2015年の挑戦であるコーポレートフェローシップと3月末のCivic Tech Forum 2015についてお伝えしました。
プレゼンスライドはこちら
プレゼンテーションでは、僕がCfAに関心を持つきっかけを作ってくれたJenniferさんにも聞いていただきました。彼女のTED Talksに出会わなければ、僕の人生でここに来ることはなかったと思うし、まさか本人を前にプレゼンすることになるとは2年前には想像もできませんでした。彼女のプレゼン・コンテキストが僕を連れてきたんだと思います。
TEDの精神である”Ideas worth Spreading”を体感した瞬間でした。

CfAのスタッフの方々には突然のインターンシップをさせていただいただけでなく、お忙しい中、僕から提案させていただいたことにも快くほとんどのことに対してご協力いただき本当に感謝です!
今度は僕が日本にこの経験を還元できるように精一杯頑張っていきたいと思います。
I appreciated everything of Code for America .This internship is my treasure in my life.
おわりに
最後まで読んでいただきたありがとうございました。
まだまだお伝えしたいこともありますが、今回のご報告はこの辺で。
改めて今回のインターシップで感じたいことは、米国内でのCode for ムーブメントの広がりとエコシステムとしての可能性の大きさでした。その一方、日本でのBirgadeを中心としたCfJの活動について誇りを持っていいのだと感じました。社会への大きなインパクトを与えたり、持続可能な活動にはCfJも日本のBrigadeもまだまだ辿りついていないかもしれませんが、CfJ設立からこれまでの約1年半の活動について、米国の方々からは「なぜ日本はたった1年半でそこまでCivic techが広がったのか!?すごいじゃないか!!」というフィードバックを得ることが多かったです。日本の活動は米国やオープンデータの推進が進む欧州に比べるとまだ若いかもしれませんが、自信をもって今後も目の前の課題に取り組んでいけばいいのだと感じました。今回学んだことをナレッジ化したり、Code for Japan / Nantoで組織化していくことも大切ですが、それ以上にCode for の活動に対して「自信を持つこと・志を保つこと」を伝えていくことが僕の役割かと考えています。
帰国後の3月12日の第63回Code for Japan井戸端会議でもここに書ききれなかったことをお伝えしましたが、今週末のCivic Tech Forum 2015のLTでも少しお話させていただきますので、ご関心のある方は3月29日(日)に科学技術館にお越しください。LT後のアンカンファレンスやAsk the Speakerのコーナーでご質問等にお答えできると思います。

改めて今回の機会をつくっていただいた関係者のみなさま、ありがとうございました。
Code for Japan / Nanto松本