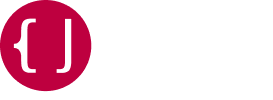グラレコ、編み物と続いたこのインタビュー企画。では、本職がエンジニアの方はどんな活動をされているのでしょうか。CODE for AIZU、Code for Fukushimaで活動している徳納弘和さんにお話を伺いました。

子ども、女性、市民、を対象に新しい世代へ
徳納さんはとても活動的な印象です。最近はどんなことをされているのですか?
今、一番力を入れているのは子どものプログラミングです。CoderDojo(アイルランド発祥の子供たちの為のプログラミング道場)に参加してからちょうど3年がたちました。毎月1回、会津若松で開催すると多いときは20人くらい、今年は新型コロナウイルスの影響で10人くらいですが、子どもたちが集まってプログラミングを学ぶ場を作っています。私は電子工作担当でメンターとして参加しています。隣町の喜多方でも月1回開催しているのと、会津から1時間くらいの場所でも2箇所あって、そこにも年に数回は顔を出すようにしています。
電子工作は子どもが楽しくできそうですね。会津若松のCoderDojoではどんな風に学べるのですか?
CoderDojoのいいところは、いろいろなものがあって、自分の好きなものをやっていいところです。いろいろあればその中から1つくらいは興味あるものが出てきます。とりあえずやってみて、飽きたら別のものに変えてもいいんです。そんなゆるい感じが好きですね。子どもたちの発想はすごくて、大人の想像を超えるものもでてくるので、大人たちはいつも驚かされます。そんな子どもたちを見ていると、技術者ってどう生きていけばいいんだろう、自分が差別化できるところってどこなんだろうと考えさせられますね。
その他にはどんな活動をされていますか?

あとはDjango Girlsです。女性を対象にプログラミングの体験と学ぶ機会を提供している国際的なコミュニティで、東京で開催されたワークショップにメンターとして参加させてもらいました。メンターは男性もOKなんです。そのワークショップがとても面白かったので、福島でもやろうと思って知り合いの女性と始めました。多いときで15人参加してくれました。今まで(2020年8月現在)7,8回やっているので、延べ50人くらい参加してもらっています。「1時間かけて来ました」「こんなの欲しかったんです!」って言ってもらえるので嬉しいですね。あまりプログラミングに触れるきっかけがない人が多いのかなって思いました。子どもはもちろん、大人にも体験してほしいんです。
Django Girls は女性向けなので、女性ばっかりって言う人もいます。でも、男の人ばかりのところだと入りにくかったりするじゃないですか。いろいろな場が必要だと思っています。
市民ファシリテーターもされていますね。それはどのような活動ですか?

シビックテックを広げるために、普及活動みたいなものもやっていかないといけないなって思いました。社会を良くすることがシビックテックの目的なので、自分の活動をITに限る必要はない。なにかやりたいなと探していたら、Code for Japanの市川さんが講師にこられた「ファシリテーター養成講座」を見つけ、参加しました。それがきっかけで市からちょこちょことお声がかかるようになって、市民ファシリテーターとしての活動が始まりました。会津若松市の広報で呼びかけで集まった市民の方たちのまちづくりや暮らしについてなどの対話をファシリテーションしています。
38歳から半導体からITへの転向
仕事をしながら地域と関わるいろいろな活動をされているんですね。もともとはIT系ではなかったそうですが。
実は、生まれは大阪で育ちが奈良なんです。元々は半導体業界の技術職をしていて、2,3年毎にあちこちの工場に行く、いわゆる転勤族で、会津若松に流れ着きました。会津若松に来る前は2週間で会社辞めてやるって思っていたけど、結局、育った奈良に続く長さです。震災のときはすでにここにいたので、それも離れがたい理由の一つかもしれません。今に至るまで、転職したつもりはないんだけど、会社が売られたり、倒産して変わったりと、会社が何回か変わっています。38歳のときに会社が倒産して、半年くらい自宅待機になったんです。自分がいた会社が倒産するのは初めてじゃなくて、やっぱり、仕事がなくなるのが怖いんですよね。働き始めた頃にバブルが崩壊して、アジア各国が追い上げているときで、これはまずいぞって若い時から常に思っていました。だから、大人になってからこんなに時間とれることはあまりないので、逆にチャンスだと思い、本格的にITの勉強をはじめました。
CODE for AIZUの活動を始めたキッカケを教えて下さい。
仕事だけだと成長に限りがあると気がついて、勉強会に参加するようになりました。そこで、藤井さんと前田さんに出会い、CODE for AIZUの活動に参加しました。最初のころから、二人が前面に出てくれていますが、CODE for AIZUは特に代表者が決まっていないんです。私も初期メンバーなので最初からいますが、現時点で誰がCODE for AIZUのメンバーなのか、よくわからないですね(笑)プロジェクトが始まるのも、定例会で「○○プロジェクトを始めましょう」ではなくて、相談する場が作ってあって「こんなのやりたいです」と言うときもあれば、いきなり「やります」って言うときもあります。相談する場でやるかどうかを決めるというよりは、基本的にやることが前提で、やり方とかいつやるかなどを相談する場なんです。私達はなにかしないといけないのではなくて、やりたいことがあるから集まります。
CODE for AIZUは「行動 for 会津」と表示していますね。「行動」となった背景を教えてください。
CODE for AIZUを創ってから1年がたって振り返りをしました。そのとき、エンジニアが集まって、作りたいものを作っていて、結局、独りよがりのものになってしまった、という反省点が出てきました。その反省を活かし「これからはちゃんと町に出て人の話を聞きに行ったり、体を動かそう。ちゃんと行動しよう。それならいっそのこと、名前も変えようか。よし「行動 for 会津」にしよう!」となりました。

CODE for AIZUが始まってから走り続けている徳納さんの活動の原動力は何ですか?
震災のときに感じた無力感みたいなやつでしょうか。会社が倒産したときのことも、罪悪感みたいなものも。「もっとやれたんじゃないか」って、感じています。そういうのも原動力になっているかもしれません。あと、年齢的にも自分のことじゃなくて次の世代のことを考えたいです。社会を良くする活動をしようと思っています。
シビックテックはみんなが「効率よくしよう」と言っているところも性に合うんですよね。本職もずっとそんな仕事ばかりしてきたので。だからシビックテック界隈の人たちと何かするのが面白いんだと思います。
Code for Fukushimaも始まりましたね。
そうなんです。まだできたばかり。郡山で福島県版の新型コロナ感染症対策サイトを作った人を私がサポートしたのが始まりです。県のサイトなのにCODE for AIZUがやるのは変だし、やっぱり市区町村じゃなくて県の方が自然だよねという意見もあり、結果的にCode for Fukushimaを創ることになりました。ノリで2時間くらいで決まりました(笑)初期のメンバーは私、藤井さん、清水さん、郡山で出会ったCode+Designの方たちです。今は感染症対策サイトの維持がメインですが、これからいろいろ活動していきたいです。最近、子どもの教育でも、技術者じゃない人たちに技術をわかりやすく伝えるのにも、デザインの力が必要だなと感じています。メンバーにデザイン系の方がいるので、とても楽しみです。
今の活動が新しい世代へつながる未来
未来の話をしましょう。
いろいろな未来があるのですが、、、まずはDjango Girls 福島。本当はDjango Girlsって、女性による女性のための活動なので、私が色々やっちゃいけないんです。だから、ちゃんと女性だけでできるように整えていこう思っていた矢先にコロナで止まってしまった。これはそろそろ再開したいです。
あとは子どものプログラミング教育ですね。福島県は全国で最下位レベルの準備不足だと言われています。これはいかんだろうと、自分にもなにかやれるんじゃないかなと思うので、いろいろなところに顔だしたり口出したりしていきたいです。プログラミングをやりたい子がいっぱい出てきて、やらせたいって思う人もいっぱい出てきて、教えたい人もいっぱい出てきて、盛り上がっている未来を作りたいです。でっかい体育館やイベント会場で500人くらい集まるイベントとかできたらいいですね。自分がプレイヤーで最前線にいるというよりは、プレイヤーを生み育てたいです。
楽しそうですね。私もその場にいたいです。では、徳納さん個人の未来はどう描きますか?
去年、半分ネタでエストニアの電子市民になったんです(笑)イギリスやアメリカに仕事で住んでいた事もあって、英語もそこそこ話せます。今は英語とITのスキルが宝の持ち腐れ感があるので、活かせるようなことをしたいなと思っています。例えば、会津若松にいながら世界と仕事をするとか。そんなことできるんだってところが見せられるといいですね。
あと、欧米は住んだことあるので、別の所に住んでみたいです。もっと面白いことができるんじゃないかなと思っています。実現の可能性はかなり低く、夢みたいなことばかり言っていますが、まずは言うことも大事ですよね。そうじゃないと一歩目は踏み出せないので。

最後になりますが、これからITやシビックテックに関わろうかなって思っている人に伝えたいことはありますか?
そうですね。ITって技術なので、それを使うことが目的ではなくて、ただ手段の一つなんです。「この技術が使えるからこれをやる」のではなくて、目的を明確にしてそれをどうやって解決していくかってことなんです。何ができるか知るために、技術は知っておかなくてはならないんですけど、目的と手段は取り違えてはいけないなぁって思っています。
あとは、楽しむこと。義務感でやるのは面白くないので楽しんでやるのが一番だと思います。楽しくないと続かないですから。
そうそう、あと、いろいろな人がいるってことを想像しようってことも大事。シビックテックってなんとなく意識高い感じがしますが、みんながみんなそうじゃなかったりすると思います。それが、良い・悪いってことではなくて、みんなが同じ意識や価値観、知識を持っているわけではないということです。論理的に生きてる人も感覚的に生きている人もいるし、本当にいろいろな人がいっぱいいるんです。多くの人に知ってもらおう、使ってもらおうとするなら、いろいろな人を想像しないと行けないんです。やっぱりここは忘れないようにしながら、これからも活動していきたいですね。