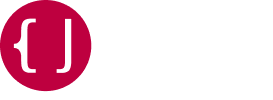産後を救い、世界を変える手助けをしよう。#codeforjapan
先日お知らせした通り、今 Code for Japan はマドレボニータさんと一緒にGoogle Impact Challengeに応募しています。Google Impact Challengeは、様々なテクノロジーの活用を通じ、社会問題の解決にチャレンジする非営利団体を支援するプログラムです。支援対象に選ばれた4団体には、Google から5000 万円の助成金が支払われます。現在一般投票を募っているところで、マドレボニータも候補者10組の中に入っています。
対象者は、みなさんの投票と審査員による審査で決まります。投票受付中ですので、みなさん是非応援いただけましたら幸いです。投票は、26日が締め切りです!
■他殺による最も多い死亡年齢は0歳
この動画をご覧ください。
他殺による最も多い死亡年齢は0歳で、そのほとんどは虐待死である。私はこの事実を知り衝撃を受けました。新しい命が家族に加わるという幸せな出来事が、虐待という悲しい事実につながるかもしれない入り口でもある。マドレボニータ代表のマコさん曰く、出産前までは母親のサポートはたくさんあるが、出産後には子供向けのケアが主体になってしまい、母親に対するケアは意識されなくなってしまうとのこと。なんとも悲しいことです。インパクトチャレンジ公開後、マドレボニータに寄せられる、「わたしも欝になりかけた」「わたしも気分が落ち込んで大変だった」という声のなんと多いことか。子供が生まれると、「家族水入らずにしてあげよう」「今は大変だろうから落ち着いたら行こう」といった気遣いでこれまでの友人との関係性が疎遠になってしまう。また、これまでしっかりと自分の人生をコントロールできてきた人ほど「なんでも一人でできる」と頑張ってしまい、SOSを上げられずに孤独になってしまうといったこともあるそうです。産後の心身の回復が十分でないことは、産後鬱、乳児虐待、早期離婚を引き起こし、 育児にネガティブな影響を及ぼします。そのような時こそ周囲のサポートが必要なのですが、日本では旧来の文化的・教育的問題から、なかなか産後ケアの必要性が認識されず、公的なケアも不足しています。
■「産後ケアバトン」でつながる母親サポート
そこでマドレボニータさんが考えたのが「産後ケアバトン+(プラス)」。妊産婦に対して、家族や友人が、産後ケアを出産祝いとしてプレゼントし、ついでに産後ケアも学べてしまう、というシステムです。これが実現すれば、今までの何倍もの人に、産後ケアを届けることができるようになり、産後うつ、乳児の虐待、早期離婚といった、不幸な事態を予防できるようになります。
本プロジェクトによって、3 年間で年間 2 万人が産後ケア教室に参加し、年間 30 万人の妊産婦とその家族や友人に、産後ケアに関する知識を届けることが可能になります。
産後ケア文化が当たり前になることで、産後鬱、乳児虐待、早期離婚を減らし、社会をより良くしたいと考えています。(詳細については http://googleandmadrebonita.strikingly.com/ へ)
■ Code for Japan として取り組むことインパクトチャレンジに応募した経緯は、前回の記事を参照いただければと思いますが、Code for Japan として考えていることは、以下の内容です。
・アプリ開発のサポートCode for Japan は開発会社ではありません。アプリ開発そのものは、別の開発会社にお願いするか、フリーランスの開発者などにお願いすることになります。Code for Japan 側では、浪江町でのフェローシップでやっているように、マドレボニータサイドに立ちプロジェクトマネジメントを行う人材を公募して派遣したいと考えています。浪江町でやっているように、公募したプロジェクトマネージャーに対するサポートも行います。
・Code for ネットワークを通じた展開Code for Japan の価値は、全国のブリゲード(ローカルCode for コミュニティ)コミュニティの存在です。ブリゲードの中には、子育てをテーマに活動しているところも多くあります。そのような地域と連携しながら、アプリ開発時のユーザーテストや、自治体との連携検討を行なっていきます。アプリが完成したのちは、ワークショップの実施なども行なっていきたいと思います。インパクトチャレンジでの助成金は、このようなブリゲードへの活動費用にも充てられます。Code for Japan ネットワークは、技術者だけの集まりではありません。自治体職員も、一般市民も、議員もいます。Code を通じて地域を良くしたいと願う、そういった人々と一緒に社会への実装を進めていくことができればと思っています。既にいくつかのブリゲードからは、協力を取り付けています。日本で成果が出たら、海外の Code for コミュニティにも波及させたいと考えています。
・データを蓄積、分析し、社会に活かす産後ケアアプリを通じて、様々なデータが取れると思います。3年で30万人(最新の目標では100万人という話も出ています)の、妊婦及び関係者に産後ケアを届けることを目標としていますが、それだけの人がこのアプリを使えば、統計情報や実態調査などにも利用することができます。そういったデータを蓄積、分析することで、必要な支援体制や公的サポートなどについてマドレボニータさんと共に提言を行なっていきたいと思います。
■ Code で社会を住みやすくCode for Japan は、シビックテックでより良い社会をつくることを目指しています。社会課題に対して長年取り組んできたテーマ型コミュニティであるNPOと連携するというのは、Code を社会に役立てるための近道です。「教室」という、徹底的にアナログな現場で、バーチャルには決してできない方法で、産後の問題解決に15年以上愚直に取り組んできたマドレボニータさんと、テクノロジー活用の方法を十分に理解している Code for が組むことで、社会をより良い場所にしましょう。このムーブメントには、あなたも参加できます。既に Code for Tokyo のメンバーの有志と Women Who Code Tokyo の有志の手によって、「マドレボニータChallenge応援団」というフェイスブックコミュニティを作るなど、動きが始まっています。インパクトチャレンジの結果がどうあれ、このプロジェクトは進めていきたいと考えています。
■ このプロジェクトを応援する方法これを読んで少しでも心が動いた方、是非ご支援いただければと思います。以下の様な支援方法があります。
皆様のご支援をよろしくお願い致します!
関