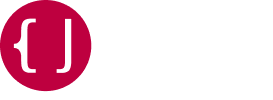はじめに
Civic Tech Fun! Fun! Report! 8月号は、Code for Amagasaki、Code for Nerima、Code for Yamatokoriyama、Code for Japanの4団体のレポートを掲載しています。
今回は、Code for Yamatokoriyama 岐阜支部長の石井さんから「ソーシャルディスタンスを保ってロボット金魚すくいPRJ」のレポート!イベント中にZOOMの中継をしていたのですが、本当に楽しそうでした。そして、Code for Nerimaの青木さんからは練馬区が主催するイベントのオンライン配信のご紹介!自治体との協働をする上で、参考になります。
その他にも、内容盛りだくさんの8月号をお楽しみください♪
協力:たださん(Code for Amagasaki)、青木さん(Code for Nerima)、石井さん(Code for Yamatokoriyama)、武貞さん(Code for Japan)
Code for Amagasaki
コロナ禍で短くなった夏休み初日の8月1日(土)に、小田南生涯学習プラザでプログラミング体験のイベントが開催されました。C4AMAが講師を務めまして子供達へプログラミングを教えて来ました。
子供相手にプログラミングの体験を行うとなると、なかなかオンラインでは難しいので、対面でのイベントとなりました。コロナ対策で、大会議室に10組(とその保護者)のみに制限したり、参加者のPCには触らない等の対策をしての開催になりました。
Code for Nerima
代表の青木です。先日、協働推進課からの要請がありまして、区が主催するイベントのオンライン配信のお手伝いをしてきました。
「つながるカレッジ」と言う練馬区の学習プログラムで今年「福祉」「防災」「農」「みどり」「環境」の分野に拡張しリニューアル(昨年までは「パワーアップカレッジねりま」で福祉の分野のみ)しました。
ところがコロナ禍で開校がおくれ、9月からとなり、公開講座はオンラインとオフラインの両方に対応で提供したいとのことでした。
【ねりまつながるカレッジ ハイブリッド開催サポート】
こちらのブログに開催日のオペレーションがまとまってますのでぜひ御覧ください。
住んでて、そして練馬区とも関わってるのですが、練馬区ってほんとIT進んでると思うのです。ところがあまりそういうことが知られていないというか、PRベタというか、大根しか無いと思われてるとか、いろいろと(笑)。
今回のポイントは現地での機材はすべて練馬区にあるもので、練馬区の職員さんたちでほとん設置。ってことは自治体であれば大体どこでもできるってことです。それで配信などちょっと込み入ったところはオタク…じゃなくて専門家集団のCode for Nerimaがサポート!といった理想的な「協働」の形となります。
公開講座はあと2回、そしてこの機会にZoomなどもきちんと覚えて、通常の少人数の講座でもオンラインの参加に対応ができるように進めていきたいとのことです。
Code for Nerimaは練馬区とのわりといい形で協働出来ていると思いますので、これからもこうしたサポートをしていろいろ情報やスキルを共有していけたらと思ってます。
Code for Yamatokoriyama
大和郡山は金魚の産地として有名な街で、商店街にも金魚が溢れています。金魚改札や金魚自販機といったユニークなものまであります。
そんな金魚好き大和郡山の夏の風物詩である金魚すくい選手権大会が、コロナの影響で中止になってしまいました。それでも「金魚すくい」はやってみたい。と、ひとつのプロジェクトが立ち上がりました。
今回はそのプロジェクトの一環で、実際にロボットを使って金魚すくいをしてみようというイベントを紹介します。
会場の柳花簾さんは古民家を改修したレンタルスペースで、金魚すくいにはもってこいの中庭もあり、とてもいい雰囲気でした。

レンタルスペースの柳花簾。ここにも金魚
今回のイベントで用意したロボット
- UFOキャッチャータイプ

糸巻き機をモーターで回してポイを前後と上下に操作します
- ロボットアームタイプ

ロボットと金魚。なかなかシュールですw
プログラミング教室に参加している子どもたちや新聞の記事をみてふらっと立ち寄ってくれた方たちで盛況でした。

子どもたちは興味津々
ポイで金魚をすくうとバランスを崩してしまう。とか、金魚を追い込むにはスピードが足りない等まだまだ、金魚すくいをするためには改良の余地はあります。それでも、ゆくゆくはインターネットを通じて完全にリモートから操作できるようにして全世界から金魚すくいを楽しめるようにする予定です。
今後もプロジェクトの展開にご期待ください。

プロジェクトメンバーと記念撮影
詳しくはCode for Yamatokoriyamaのホームページでもリポートしています。こちらもご覧ください。
Code for Yamatokoriyama 岐阜支部長 石井
Code for Japan
Civictech Challenge Cup U-22 エントリー締切り&協賛企業決定
社会課題解決をテーマにした学生向け開発コンテストの参加者募集を8月末に締め切りました。先着100名としていたものの最終日に応募が増加、105名の学生がエントリーし、チーム組成を順次行いながら、企画・開発に向けて進んでおります。8月13日に協賛企業のさくらインターネット代表田中様にゲストとしてお越しいただき学生向けLTイベントを、15日には特別協賛のクリーチャーズ小村様・小澤様・松村様をお迎えし企画立案・リテンション設計をテーマにした勉強会を開催しました。
また、特別協賛のクリーチャーズをはじめ、Google、アカツキなど9社に賛同いただき、パートナーとして協力いただくことが決定しました。今後の学生チームの開発プロセスに対する勉強会講師やメンタリングなどでお力添えいただきながら、最終審査会では各企業から企業賞を、全体からは大賞を選出していく予定です。
Code for Japan Summit Online 告知サイトオープン
2014年から東京、横浜、神戸、新潟、千葉と全国各地で開催してきたサミット、7回目は愛知開催を予定しておりましたがコロナの影響もあり、今年度は初めての全面オンライン開催を予定しております。各地で長年ブリゲード(Code for XX )として活動している人はもちろん、コロナがきっかけでシビックテックを知った初参加の学生やエンジニア、主婦、公務員など様々な方にご参加いただけるよう、有志コントリビューターが50近くのセッションを立案しており、幅広いテーマでそれぞれが用意しています。
キーノートは台湾デジタル担当大臣唐鳳さん、慶應義塾大学教授の宮田裕章さんをお招きし、今年のシビックテックの変化を振り返りつつ、これからのシビックテックについてお話しいただく予定です。
参加無料のオンラインイベントですので、是非遊びにいらしてください!
オンラインワークショップ開催
全面オンライン開催となるサミットの開催に向けて、Code for Japanと共に準備を進める共催の東海エリアのブリゲードと共同でイベントを開催しました。Code for GIFU・Code for Nagoyaから2名が講師を務め、活動紹介動画を企画→設計→編集→アップロードまで全参加者が完成させるまでをサポート。勉強会終了時間までに無事全員が動画を制作することができました。今後各地のブリゲードの動画化を声かけし、サミット当日初参加の全国各地からの参加者が各プロジェクトがどんなことをやっているのか把握し、関心があるブリゲードに入れるよう引き続き取り組んでいく予定です。(イベントレポートはこちらhttps://note.com/mamisada/n/nbe5e6541bfd5)
ブリゲードの新規加入
京都・印西・岩手・SAKEが新たにCode for Japanのブリゲードになりました。元々Code for XXという組織は誰でも各地域で立ち上げることができるのですが、一定期間の活動と複数名のメンバーが存在し、申請があれば、Code for Japanのブリゲード(https://www.code4japan.org/brigade 元々は消防団の意味、Code for Americaも各地域のコミュニティをブリゲードと称している)として連携をしていく形となります。今回はCode for Kyoto、Code for Iwate、Code for Inzai、一昨年の新潟開催サミットで発足したCode for SAKEが新たに仲間になりました。これまで地域名称のブリゲードはあったのですが、テーマ(各地域の酒蔵と日本酒好きを繋げながら、日本酒にまつわるオープンデータを広める)のチームの登録は初めてでした。