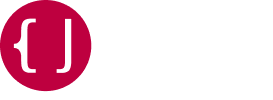今日は、Code for Japan の社員総会でした。

(総会の模様)
早いもので、Code for Japan を設立してから5年になります。日本におけるシビックテックは、どれくらい進んだでしょうか。
5年前には、「シビックテック」という言葉をGoogleで検索しても、ホンダのシビックのページが出てくるくらいでしたが、今では、たくさんの検索結果がヒットします。関連検索キーワードも様々。

(馬まで!)
Code for Japan の5年間の歩みと、これからについてを書いてみたいと思います。
各地に 70以上の Code for ネットワークができた
2018年12月16日現在、HPに表示されている Code for コミュニティ(ブリゲイド)は、74地域。(少し前まではプレゼン等では80以上と書いていましたが、活動を停止した地域を外しています。)以前Mediumで書いた通りCode for の各コミュニティはCode for Japan の下部組織ではなく、それぞれの地域ごとに主体的に活動されています。ヒエラルキー型の組織ではなく、草の根的なネットワークであることが、とても良い効果を生みつつあると思います。Kanazawa、Aizu、Sabae、Chiba、ふじのくに/Numazu、Kobe、Toshima など、それぞれ地域ごとの特色があり、画一的ではないところがとても良いですね。
各地のコミュニティでは、下記に書いたようなさまざまな活動が生まれています。Code for Japan では、各地のイベントやワークショップに対して補助を行ったり、地域ごとのミートアップや、後述する Code for Japan Summit の場での情報共有なども行っています。

Code for Japan が地域の課題解決をするのではなく、あくまでその地域に住む人達が主体的に関わることで課題が解決されていくという、シビックテックの最も根幹を成す部分だと思います。
5374.jp、保育園マップなどの市民発アプリも生まれており、オープンソース化することで広がりを見せています。
行政側のシビックテックに関する意識が高まった
Code for Japan として内閣官房や総務省のICT活用に関するさまざまな委員会に参加したり、各地のブリゲイドの自治体との協働事例が増えてきたりといったことから、行政の戦略の中にもシビックテックという言葉が出始めています。
特にオープンデータ活用については、市民との対話や共創が重要であるという点はだいぶ浸透してきたのではないでしょうか。Code for Japan は総務省の地域情報化アドバイザーにも登録しており、いろいろな自治体に講師を派遣してきています。地道な布教活動がだいぶ実ってきていると感じています。
また、3年前に Code for Japan が神戸と協力しながら始めたデータアカデミーは、昨年度から総務省の事業の一つとして、2017年度は11自治体、約180人が参加。2018年度は39自治体に展開中です。総務省ではなく、自治体の独自予算によるアカデミー実施も増えてきています。

(自治体総合戦略2040のページから抜粋。プラットフォーム・ビルダーへの転換が必要と強く記述)
行政内の外部人材の活躍が目立つように
Code for Japan では、雇用流動性の少ない行政に対して、外部人材が関わることを強く推進してきました。その一つ、フェロー派遣については、浪江町で2014年に1人目の派遣が始まりましたが、その後神戸市にも2017年からフェローを派遣しています。(自治体から直接雇用されています)
現在は浪江町にはフェローは派遣していませんが、神戸市のフェローである砂川さんは庁内でも高く評価されていますし、浪江町に派遣後神戸市に写った吉永さんも引き続き活躍しています。
私自身も、3年前から神戸市の「チーフ・イノベーション・オフィサー」として、非常勤職員として働いています。
また、企業人材が週1日程度のペースで3ヶ月間自治体の職員になって働く、「地域フィールドラボ」も、自治体、企業双方から高い評価をもらっています。これまで、51名のフェローが20近くの自治体に派遣されてきました。アクティブラーニング型の人材育成プログラムとして実施していますが、自治体にとっては、外部の知恵やネットワークから新たなことを学べるとともに、企業側からは真の課題の発見や新たな事業の種の発見などの成果につながっています。
フェロー同士や受け入れ自治体同士のコミュニティも生まれ始めています。
Code for Japan のこれからについて
さて、これまでの5年間は、一言で言えば「準備期間」だったと思っています。各地にネットワークができると同時に、Code for Japan 自身もフルタイム2名の他、様々なプロジェクトに関わってくれる人が増えています。更に、今期からは元総務大臣補佐官の太田直樹さんに理事に加わっていただきました。
次の5年では、より本質的な部分で成果をだしていきながら、同時にスケールもしていくフェーズです。縦、横ともにしっかりと根を伸ばしていくことを考えています。
データアカデミーはさらなる高みへ
先日裾野市とデータを活用した政策立案を行うためのパートナーシップを結びました。データアカデミーを更に発展させ、EBPMや総合計画づくりもお手伝いをしていきます。
データアカデミーの良いところは、原課の職員自身に仮説を作ってもらい、実際のデータを使って分析をしてもらうことです。ときにはワークフローなども書いてもらいます。答えをもらうのではなく、自分で答えが出せるようにする。そういった経験を現場の職員とともにすることで、我々自身も自治体の現場の課題に詳しくなることができます。

裾野市との パートナーシップ
また、講師を育成すると同時に企業などとも連携しながら、より多くの自治体にデータ活用のワークショップが展開できるように、体制を整えていきます。
STO:人々をテクノロジーでつなぎ社会課題を解決する専門職
昨年から副理事の三本裕子さんが中心になって仕込んできた事業が、ソーシャル・テクノロジー・オフィサー(STO: Social Technology Officer)創出プロジェクトです。
社会課題の現場で長年取り組んできたNPOですが、アンケートを取ったところ多くの人が「技術の速さについていけない」「そもそも何ができるかわからない」「どれくらい投資すれば良いのかわからない」「任せようにも技術人材が採用できない」という課題を上げていました。
リソースの限られた組織だからこそ、ITをうまく使い本来やるべきことを伸ばしていくべきなのですが、なかなか現状では難しい状況です。そこで、社会課題にも詳しいCTO職として、STOという職業を新たに創出することを目的として、マッチングやスクールを実施しています。
具体的には、経営層に対してIT投資の優先順位付けをしたり、現場の適用も含めて実現可能な方法を共に考えたりといった業務を行ってもらいます。
今後、この活動をさらに本格化させて、課題解決を加速させていきたいと考えています。
GovTech を推進
おそらく、来年は GovTech(ガブテック) という言葉を耳にする機会が多くなると思います。GovTech は今流行りの「○○テック」の一つですが、文字通り「Government」x「Technology」を表しています。
例えば、Code for Japan では中小企業庁のシステム開発をアジャイルプロセスで行っています。私がチーフ・イノベーション・オフィサーとして神戸市で行ってきた、Urban Innovation KOBE も、GovTech 的なプロジェクトがとても多く走っています。
シビックテックとGovTechはオーバーラップする部分も多く、とても相性が良い活動だと思います。スタートアップ、NPO、行政をSTOがつなげていく、そんな活動に繋げられればと思っています。
ロビイング2.0
これまで Code for Japan があまり力を入れられてこなかったのが、政策提言などのロビイング活動です。リソース不足や、やり方がわからない、政治に巻き込まれるよりも現場主義的であった、などの理由があったのですが、デジタル化を阻む様々な要因がある中で、条例や法案の改正などにより積極的に声を上げていくことも必要だと考えています。
データアカデミーなどを通じて、より具体的な障壁に触れたり、データを扱えるようになったことも大きいです。
最近は新しいスタイルでロビイングを行うような団体も増えてきたので、そういった団体と連携しながら、データの見える化や、建設的な議論を行うためのワークショップ開発などを開発していきたいと思っています。
この分野については、台湾のg0v(ガブゼロ)が得意としているので、連携をしていきたいと思っています。
その他、海外との連携や若手の育成、サミットなど、さまざまなことがあるのですが、十分長くなったのでこれくらいにしておきます。
皆様、今後とも一般社団法人コード・フォー・ジャパンをご支援いただけましたら幸いです!