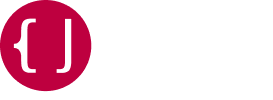データ連携基盤をテーマにしたイベントを開催しました
「ITで、社会の願い叶えよう。」のTIS株式会社と共催で、Make our Cityのデータ連携基盤をテーマにしたイベントを6月6日に開催しました。本イベントを皮切りに、スマートシティのエコシステムには欠かせない、FIWAREやデータ連携基盤を取り巻くエンジニアのコミュニティを醸成してまいります。イベントレポートとともに、当日の動画も掲載しておりますので、データ連携基盤について「もっと知りたい!」、「こんな使い方はあるだろうか?」と思っていただけた方はCode for Japanのslackコミュニティの「♯proj-fiware-community」チャンネルにぜひご参加ください!
(slackコミュニティへの参加方法は団体サイトの説明ページをご確認ください)
スマートシティのエコシステムにおける両者の役割
TISインテックグループのTIS株式会社とシビックテックを推進する一般社団法人コードフォージャパンは、地域課題の解決を図る持続可能なまち作りに向けて、地域コミュニティやスマートシティのエコシステム醸成を目的に包括連携協定を締結いたしました。
TISは事業を通じて解決を目指す社会課題の一つとして、都市への集中地方の衰退を掲げ、
様々な企業や団体、地方自治体と取り組みを進めています。
Code for Japanでは、市民中心のまち作りを行うMake our Cityプロジェクトを推進しており、TISのIT技術と、Code for Japanのコミュニティ作りのノウハウが合わさることで、シビックテックによる持続可能な地域作りを実現するためにより実践的で包括的な分野でのサービス提供ができると考えています。
対談「日本でのFIWARE普及に足りてないもの」
冒頭、TIS株式会社油谷実紀とCode for Japan関治之の2人によるキーノート対談では、「日本でのFIWARE普及に足りてないもの」と題して、2社の問題意識と今後の取り組みの方向性について、関が問いかけるスタイルで対談が始まりました。
関/包括連携協定を結ばせていただいたわけですけれども、今回TISさんとして今回の提携の中で特にスマートシビックテックとか、そういったものに対して、期待していただいているところというのを聞かせていただいてもよろしいでしょうか?
油谷/やはりその地域のコミュニティこそが主役であり、我々SIerとしてはその基盤を提供するっていう形になるので、一緒に作り上げていくためには主役の人たちときちんと話をしていく必要がある。それがシビックテックという形で、Code for Japanの方もエンジニアであったり、元々エンジニアではない方もいらっしゃると思うので、そういった方たちと一緒にやるっていうのが、近道というかですね、そういうふうにやっていくことこそが地域で、皆さんみんなで物を作り上げていくことになるのかなと考えています。
TISでは会津に拠点を設けて、今回のイベントでも司会進行を務めている住吉美樹さんを中心として、「地域の人たちのために、課題解決のプロセスの一部を担えないだろうか」という取組を続けられています。なぜ、大手のSIerのひとつして数えられる企業が、シビックテックに共感され、そこにどんな可能性を見いだしているのか、CfJ関が再び問いかけます。
関/既に会津でやってきたこと、それをもっともっと強化したりとか、いろんな地域でやっていきたいみたいな感じでしょうか。我々は Make our Cityというプロジェクトをやっているんですけれども、今回の提携を通じてそこにどんな期待があるのでしょうか。
油谷/やはり自分たちだけですと、例えば会津とかそういうところでやったときに、他地域のいいところを一緒に参照したり、他の場所の方たちと一緒に作り上げるといったことが、なかなかできないです。そういう意味でも、Code for Japanと一緒に進めることに価値があると思っています。
この後、オープンソースの活用やDataOps(データオプス)の可能性などにも話は進み、対談は大いに盛り上がりました。
政府相互運用性フレームワーク(GIF)とは
ここから先は、パネラーとして新たにゲスト2名を迎えて、パネルディスカッションへと進みます。デジタル庁でデータ戦略を統括されている平本健二 氏より、 GIFの取組の概要と目指すところについて、まずはインプットトークをいただきました。
実は突然現れたものではないGIF、そこに至る取組み
デジタル庁が発表したこの相互運用性(Interoperability)の取組みとは、実は真新しいものではありません。東日本大震災をきっかけに、語彙(vocabulary)の揺れがデータの相互運用において問題になるということがわかり、経済産業省とIPA独立行政法人情報処理推進機構が中心となってプロジェクトが進められていたと言うことを、当時から有識者として関わっておられたインフォ・ラウンジ株式会社 小林巌生 氏が補足します。
小林/実は、IMI(共通語彙基盤)っていうプロジェクトがありまして、平本さんからご紹介いただいたGIFの中にもですね、共通語彙基盤で検討された資産というものが取り込まれています。今後おそらく継続的に発展していくというふうに、思っております。 この「語彙」というのは要するに、データ交換するときに互いに言葉がちゃんと通じるように、あらかじめそのデータの外側のところにきちっと、用語の一覧と意味用法をまとめて整理しておくというものです。これをIMI(共通語彙基盤)と名付けて策定を進めてきました。
関/今まで、行政がこういったデータを取り入れ難かったものとして、データがその自治体ごとに標準化されてないとか、利用するときに都度の変換が必要ということがありました。広くいろいろな自治体のデータを同じように扱うのが難しかったのです。そういう意味だとこういうのがきちんと提供されて、実際に使われていくことになるといろいろビジネスチャンスが出てくるんじゃないかなと思います。
どういうところに、どんなデータが必要なのか
そのビジネスチャンスはどこにあるのか。その一つの可能性として、日本の強みとしてのロボティクスやセンサーデータについて話が及びます。ロボットのセンサーデータなどでFIWAREを活用されているTIS油谷実紀 氏が、その取組みについて紹介してくださいました。
油谷/ロボットについてはロボットの公道走行っていうのが、今の国会で法律が通ってですね、多分これから1年とか2年で公道走行が普通になってくるという時代に来ています。公道走行ロボットには、正しいデータが必要です。まずは歩道をちゃんと走らなきゃいけないですし、どんな段差があるか、それを乗り越えられるかなど、まだまだこれからです。そういった新しいデータが必要だとか、このデータはあんまりいらないとか、もっと厳密にデータが必要みたいな話が、これからどんどん出てくるんじゃないかと思います。
平本/そうですねまさにロボットとの関係ってのは僕たちもすごく興味を持ったところで、事前に測れるところもあるし、ロボットが走行してるうちにそのセンサーで測定した結果をフィードバックするってのもあると思ってて、センサーデータってやっぱり面白いし、日本の強みだと思うんですよね。そこはぜひ日本の強みだから生かしたいと思ってます。また、センサーデータについてもいろんな標準があるんです。けれども、これどこまで書いたらいいのかなってのは僕たちも悩んでいるんです。工場の中のセンサーの書き方というのと、路上のセンサーの書き方とかいろいろあって、それぞれにレベル感があるような気がするんです。そういうところはまさにTISさんとか、他のセンサーを扱ってる企業さんのノウハウによって、こういう場合だったらこのレベルの項目までやりましょうというのをですね、うまく整理できていけたらいいなと思ってます。
オープンソースとオープンデータ、そして共通の基盤でゲームチェンジを生む
ある地域で作った物がオープンソースで提供されることで、他の地域でもすぐに使えるようになる。その結果としてマーケットがどんどん大きくなっていく善循環がまわっていく、こういうモデルに変化していく兆しが見えてきていることを、 Code for Japan関が指摘します。
平本健二 氏/僕もゲームチェンジっていう点で、今回のGIFとかFIWAREのプラットフォームがすごい重要だと思っています。今までこういうスマートシティのプロジェクトをやってると、うちってもう相当ビハインドしちゃってるんですよという自治体の方がたくさんおられました。我々とても追いつけないっておっしゃりますが、でもそういう人たちでも、これからデータをひたすら整備すれば、あとはオープンソースを活用して基盤を導入して、自分たちの課題に合った良いものを持ってこれるわけです。もしかしたら一番出遅れてた人たちが、一番いいのかもしれないんですよ。
小林巌生 氏/今まで自治体ごとに同じようなアプリケーション住民サービスの調達っていうのをやっているわけですけど、今現状は。これが相互に開発したプログラムとか、要するにデータの流通だけじゃなくて、開発したプログラム自体も相互に交換し合って、一つのオープンソースをみんなで使い合って育てていくような、そういう文化みたいなのができたら僕はいいなというふうに思っています。自治体から国へ、自治体と自治体、また企業と国そういったいろんなプレイヤーがいる中で、リソースを分け合ってうまく一つの技術とか、プラットフォームを育てていく、これがやっぱりエコシステムの醸成には絶対に必要なんじゃないかなというふうに思います。
これ以外にも、
- デジタル社会のために、どうして技術基盤が必要なの?
- FIWAREのデータ連携基盤と、オープンデータは何が違うの?
- データを使いやすい基盤とは?
といった話題がパネルディスカッションでは話し合われました。その内容はYouTubeからご覧いだけますので、ぜひご覧になってください。

第2部 FIWAREハンズオン
パネルディスカッション後、第2部としてFIWAREのハンズオンも実施されました。このハンズオンにおける資料は、以下からご覧いただけます。