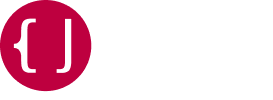2023年1月27〜29日に富山市役所と一般社団法人コード・フォー・ジャパン(以下CfJ)は富山市里山ハッカソン2022 in小見を開催いたしました。
「イキイキと自分らしく暮らせる小見(ウェルビーイング)」×「関係人口の関係性構築のきっかけとなるような製品・サービス」をテーマとし、2022年12月3日にオンラインでアイデアソンを実施。富山県内に限らず、県外からの参加者も多く、遠い方は九州から参加してくださり、合計30名ほどの方々が対面でのハッカソンに3日間取り組みました。
1日目 ~小見について知る~
小見に馴染みのない参加者も多いため、初日は小見地区をより深く知ることを目的とし、富山市大山歴史民族資料館と富山県立山博物館へ施設見学へ行きました。
資料館では大山地域の三賢人(※1)についてや、常願寺川の治水と発電、有峰、大山地域の鉱山などについての展示があり、この地域がどのようにして発展していったのか、かつてこの地区の人々はどのように生活していたのかを知ることができました。
博物館では信仰の山として崇められてきた立山についての展示や、立山信仰の舞台となった立山の自然と人間との関わりについての展示を見学しました。
小見について学んだ後は、小見コミュニティーセンターへ戻り、各グループの中間発表を行いました。
中間発表のあとは地元の方々を招き、富山の鮮魚をいただきながら歓談の時を楽しみました。小見の歴史や今感じている課題感など直接地元の方からお話を伺うことのできた貴重な時間となりました。
※1:三賢人:山岳ガイドの宇治長次郎、高野山金剛峰寺菅長の金山穆韶(ぼくしょう)、槍ヶ岳開山の播隆上人
2日目 ~開発作業日~
2日目は終日開発にフォーカスする形でしたが、外に出てフィールドワークへ行くグループもあれば、ひたすらパソコンに向き合って作業に集中するチームも、それぞれのチームらしい過ごし方がありました。
午後からはメンタリングの時間があり、CfJ理事の太田さん、西会津町CDOの藤井さんがメンターとして各チームに入り、多角的な視点からのフィードバックやアイディアを共有してくださいました。客観的な意見や刺激を受け、企画の解像度が上がっていき、チームの議論もラストスパートに拍車がかかりました。
夕方には各チームから進捗報告を行いました。中間報告からかなり進化し、企画が形になりつつあるチームや、すでにプロトタイプが完成しているチームもあれば、ガラッとピボット(方向転換)し、再スタートしているチームもあり、其々の状況が共有されました。
3日目 ~最終発表~
最終日は雲一つない晴天に恵まれ、綺麗な雪景色を眺めながら午前中は各チーム最終調整に励みました。午後の最終報告会には地元の方々やメディアの方々も観覧にお越しいただき、会場がいっぱいになったところで発表がスタートしました。
「小見の関係人口を増やす」という共通のテーマのもと、どのチームも限られた時間内で、とても完成度の高いプロトタイプをつくりあげ、発表してくださいました。
それぞれのチームには賞が与えられ、内容は以下となります。
小見地区賞:「ただいま小見〜I’m back Justnow〜」
小見地区の元住民をターゲットとし、関係人口を増やすために、小見の情報をワンストップで参照できるサイトを作成。地域の歴史、文化、現在の情報が一元化されている。
地域の方々でコンテンツ(ブログ投稿・写真、位置情報、感情をセットで投稿)を作成し、双方向での交流も可能。
里山賞:「音のおみやげ」
関係人口を増やすために小見地区だけでなく、全国の他の地域と協力して魅力を伝え合うことを目的とし、音を切り口に大自然の音、里山の生活音、昔話などを発信できるプラットフォームを作成。
ある地域の音をきっかけにアプリをインストールした人が、別の地域の音も聴いてみるというサイクルを回すことで、それぞれの地域の関係人口が入り交じる状況をつくることを狙いとしている。
審査員賞:「キングオブ小見」
小見地区の魅力を味わいながら家族の仲を深められる長期的なイベント。
関係人口の関係性構築には、まずは、小見地区に住む人々が小見の魅力をより深めて盛り上がることに焦点を当て、小見地区にまつわる様々な課題「オミ・クエスト」を小見地区に暮らす人々に考えてもらう。そして県内外の人たちに小見地区に来てもらい、現地の人とのコミュニケーションを通して課題に取り組むことで、参加者と小見地区に暮らす人々とのつながりを深めることを目的とし、イベントで使うクエストが掲載されたアプリを開発した。
Code for X賞:「OMI CUP」
子供向けのスキージャンプ大会を企画。小見関係人口の対象をスキージャンプの大人の競技者ではなく小学生の親子とすること、また長期滞在による地域とのふれあい増加を図ることで、小見地区を活性化させることを目的としている。
スキージャンプ大会で活用することのできるセンサーや画像をAIが解析できるアプリを開発。ジャンプ台に設置した多くのセンサーや、ドローンに搭載したカメラからの情報をAIが解析し、それぞれの児童にあわせたきめ細やかな指導が実施可能となる。
ペロリッチ賞(※2):「Oh!見たことない料理ができた」
小見との関わりある人を増やすために、郷土食材を小見地区以外の人達が郷土食材を作り、山岳信仰や伝説・歴史を織り交ぜた収穫祭のようなことができたらいいという着想を元に、新しい価値観での好奇心をくすぐる調理を創出するアプリ。小見の郷土食材を使った料理を通じて、小見地区の山岳信仰のスピリチュアル性を想起させるような体験ができるサービス。
※2 ペロリッチ:富山市のキャラクター http://perorich-toyama.com/
参加者からの感想
「チームみんなで楽しく開発でき、雪国特有の体験も色々できました。」
「はじめて会った人たちとチームを組んで、アイデア・コンセプトを練り上げ、ひとつのモノを作り上げる、素晴らしい経験ができたと思います。プロダクト実装時に使用したローコードツールは、自身の職場にもフィードバックしていきたいです。」
地域に暮らしている方々とハッカソンに各地から集まった参加者が、内からの視点と外からの視点を織り交ぜながら、「暮らし」や「関係人口」を考えるハッカソンとして企画・運営しましたが、各チームもバックグラウンドの異なるメンバーたちと協力し、素敵なプロトタイプを発表してくれました。今後も、このハッカソンで終了ではなく、継続して開発を進め、より多くの方々に小見の魅力を知ってもらえるきっかけとなることを願います。